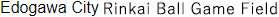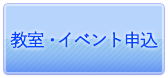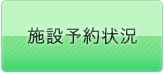疲労を感じるサインについて
疲労を感じるサインについて

令和 6 年度、第 5 回目のコラムは「疲労を感じるサイン」についてです。自
分で自分のことはわかっているつもりでも実は気がついていないことも。疲れ
ている時私たちの身体は、いろいろなところからサインを出してくれます。そ
のサインを見逃さないためにも、「自分だったらどうだろうか?」と考えてみ
てください。
疲労のサイン
寝ているのにはずなのに眠い、朝起きられない、お腹が空かない、だるいので
やる気が起きない、イライラが止まらない、肌荒れや口内炎、便秘や下痢など
の症状が一般的なものになります。
疲労のサインが続く
疲労のサインを感じとり、すぐに休息・休暇が取れる、短時間でもリフレッ
シュできれば良いのですが、現代ではなかなか難しいことが多いですよね。症
状の辛さや感じ方は人それぞれですが、身体を休める・回復させるために睡眠
はとても重要です。その睡眠ができなくなる、質が悪くなると朝起きられなく
なる、食事が食べられなくなる、集中力が低下するなど悪循環となってしまい
ます。疲労のサインに気がついて、早めに対処できるといいですね。
疲労が溜まる原因は?
運動は毎日すると習慣になり良いことの方が多いのですが、運動の強度が高
いものを毎日行うと身体は疲れ切ってしまいます。疲労が溜まり、怪我につな
がりやすく、運動の継続が難しくなることもあります。頻度と強度には気をつ
けなければいけません。また、仕事で夜勤勤務やシフト制の方も不規則な生活
リズムになりがちなので、知らず知らずのうちに疲労を溜め込みやすいです。
栄養素に関しては、野菜・果物の不足はビタミン・ミネラル不足を招いてしま
います。その結果、体調を崩しやすくなります。少しの体調不良から免疫力が
下がると風邪を引きやすくなり、流行りの感染症にもかかることがあります。
それによって体力を奪われ、元の体調に戻るまでは疲労感が残ることが多いで
す。
また、年齢が上がるにつれても疲れが溜まりやすくなります。身体の代謝が
低下するためと考えられています。
ストレスが溜まる状況も考えなければいけません。職場、家庭、友人関係な
ど人間関係によるストレスの溜まり具合と疲労の溜まり具合は切り離せない
と考えます。どこへ行っても人間関係によるストレスはよくも悪くもつきもの
です。誰にでも当てはまりますので、自分が特に疲れやすい場面や人間関係、
どのようなことが続いた時に疲れやすいかを理解しておくことが重要です。
対策方法・日頃から気をつけたいこと
今感じている不調が 1〜2週間以上続くのであれば、目に見えているところ
だけではなく他に原因が考えられる場合があるので、病院へ行って診てもらう
ことをお勧めします。
久しぶりの運動による疲労や、仕事が集中的に忙しい際の疲労など、自身で
原因がなんとなくわかっているものに関しては状況を見つつ、その症状が長引
かないようケアは必要です。
その際上記でも述べましたが、睡眠が十分摂れているか、短くても質がよく、
日中の眠気などがないかを確認します。食事に関しては、できるだけ色々な栄
養素を摂るように心がけることが大切です。忙しい時はなかなか難しいかもし
れませんが、外食やお惣菜をうまく利用し、できるだけいろんな食品を摂るよ
うにしましょう。食べる環境も大切です。20〜30 分は食事の時間を楽しんで
ほしです。その方が、切り替えにもなり次に行うことへの効率も上がるのでは
ないでしょうか。
疲労やストレスと共に生活していかなければならないですが、適度な疲労や
ストレスはやる気を高め、夜ぐっすり眠れることもあります。適度が難しいか
もしれませんが、何事もバランスを大切にしたいですね。
〜おすすめレシピその1〜
【切り干し大根のキムチ和え】

疲労回復に欠かせない栄養素の一つにクエン酸があります。柑橘類、梅干し、
酢や白菜キムチなどに多く含まれます。今回はクエン酸たっぷり白菜キムチと
食物繊維たっぷりの切り干し大根を和えました。食物繊維を摂ることで腸の働
きを促します。カルシウムも豊富に含んでいるので、イライラの防止にもなり
ます。何よりも食べ応えがあり、よく噛むことによって唾液がたくさん出て、
消化吸収にも良い影響があります。いつもキムチだけ食べている方には是非、
試してほしい 1 品です。
材料 1 人分
・白菜キムチ…お好み
・切り干し大根…お好み
・ごま油…お好み
作り方
1 切り干し大根を商品の指示通りに戻す。
2 切り干し大根を戻したら水分を搾り、食べやすい大きさに切る。
3 白菜キムチと切り干し大根を和えて、お好みでごま油を入れる。
〜おすすめレシピその2〜
【電子レンジ茶碗蒸し】

卵はとても栄養価の高い食品です。疲れていて食欲がない時は、少量で栄養価
の高い食材を選びましょう。出汁が効いた 1 品です。自然に近い優しい味付け
で、胃腸にも優しいのがポイントです。具材はお好みで良いのですが、今回は
豚肉と冷凍ほうれん草を入れました。豚肉には疲労回復には欠かせないビタミ
ン B1が豊富に含まれております。冷凍ほうれん草を使うことで手軽に栄養素が
摂れます。冷凍庫に常備しておくと何かと便利ではないでしょうか!
材料 2 人分
・だし汁…300ml
・卵…2 個
・豚肉ロース薄切り…3 枚
・冷凍ほうれん草…お好み
・薄口醤油…小さじ 1/2(お好み)
作り方
1 だし汁を作る。パックの場合は耐熱容器に水 300ml と出汁パックを入れて
電子レンジで 600W2 分を 2 回ほど行う。様子を見ながら温める。
2 1のだし汁をさます。
3 豚肉の臭みが気になる方は、耐熱皿に少量の水を入れて電子レンジで温め
ます。ゆでこぼすまではいかなくても、一旦温めることによって嫌なにお
いを和らげることはできます。
4 卵をできるだけ泡立てないように混ぜます。
5 冷めただし汁に卵をそっと流し込み混ぜます(薄口醤油を入れる場合はこの
際に入れてください)。お皿に混ぜた卵液に入れ、豚肉・冷凍ほうれん草を
そのまま入れます。
6 軽くラップをして電子レンジで温めます。500W1〜2 分から様子を見て
温めてください(卵は温めすぎると吹きこぼしがあるので注意してくださ
い)。
7 薄口醤油を入れない場合は完成したものに少し塩を振ると美味しいです。
以上