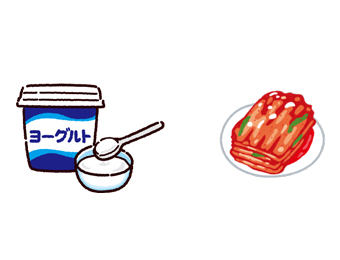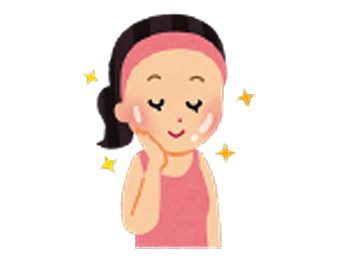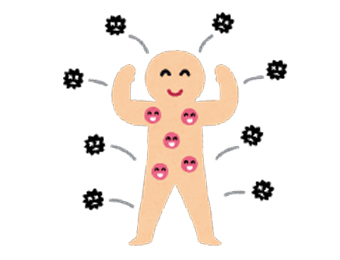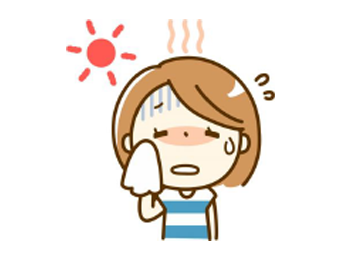新たに運動を始める時の注意点について
新たに運動を始める時の注意点について

令和 6 年度、第 4 回目のコラムは「新たに運動を始める時の注意点」につい
てです。運動という言葉を聞くと少し億劫になる人もいるかもしれません。も
し運動習慣がない人は、運動量を増やすという考え方ではなく、今よりも少し
ずつ身体活動量を増やす観点を持ち、まずは無理なく動くことを続けていきま
しょう。
健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023
このようなガイドラインが厚生労働省から提示されています。交通手段や家電
製品の発達により、日本人の日常での身体活動量は低下しています。身体活動
量の低下は糖尿病、高血圧や脂質異常症に大きく影響することがわかっていま
す。運動は大切だけど、なかなかできないという人に向けて「どれくらい」「ど
のようなことを」実施すれば良いかの具体例が掲載されています。健康寿命を
伸ばすために、今より 10 分多く身体を動かすことも推奨しています。是非、
一度確認してみてくださいね。
無理をしない
無理をしないことで「継続」できます。無理をして怪我をすると、せっかく
始めようと思った気持ちも低下します。運動の目的は人それぞれですが、健康
のために何か始めようと思っている人であれば尚更です。少しずつ、少しずつ
時間や強度を高めていくようにしましょう。「無理はしない」は合言葉です。
日常生活のどこで身体活動を増やすことができるか?
先ほど述べたように、まずは日常生活で少しずつ活動量を増やしていくこと
も重要です。ラジオ体操をする、1 駅分歩く、自転車を利用する、階段を利用
する、テレビを見ながらや家事の合間にストレッチをするなどです。自分の生
活を見直し、どこに活動量が増やせるか考えるところから始めましょう。
運動したからと食べすぎない
運動を始めたことはとても良いことで、汗をかいた後の一杯が楽しみだ!と
いう人もいると思います。運動は健康のために始めたことでも、その後の食事
で暴飲暴食してしまってはいけませんね。農林水産省のホームページに食事バ
ランスガイドがあります。イラストで視覚的にどのくらい食べたら良いかがわ
かるものとなっています。今の自分の食べている量を把握するために確認する
こともお勧めします。
運動を始めるにあたって、最初はそこまで長時間の運動や強度が強い運動は
しないと考えます。その時の飲み物ですが、糖分が多く含まれているスポーツ
ドリンクよりは、お茶か水をお勧めします。天候や運動する場所にもよります
が、スポーツドリンクは糖分が沢山含まれていることを忘れないでくださいね。
仲間を見つける
運動を継続するポイントの一つに「仲間」を作ることもあります。1 人でも
こなせる人はそれでもいいのですが、例えば一緒にウォーキングする家族や友
達がいれば続けられる人もいます。また、1 人で運動していてもその話を聞い
てくれる人がいると嬉しいですよね。最近はアプリなどで記録してシェアする
こともできます。誰かと繋がり、それを認め合える環境を作ることも大切な要
素の一つだと考えます。
〜おすすめレシピその1〜
【豚肉のえのき巻き〜手作りポン酢かけ〜】

運動で大切なことは「継続できること」と伝えてきました。そのためにも食
事では疲労回復できる食材を使って簡単にできるレシピを紹介します。
えのきは代謝を高めて疲労を取り除く効果が期待できるビタミンB1が豊富に
含まれています。豚肉とあわせて食べるとより効果が期待できます。また、血
行を良くする働きのあるナイアシンの含有量も多く、冷え性の改善にも役立ち
ます。是非、えのきを日常的に取り入れてみてください。
材料 9 本分
下準備
・豚バラ…9枚
・えのき…1 袋
・酒…大さじ 2
手作りポン酢
・レモン汁…大さじ 1
・酢…大さじ 2
・醤油…大さじ 3
作り方
1 えのきの根元を切り、数本ずつの束にちぎる。
2 豚バラでえのきを巻く。最後にギュッとえのき合わせ、巻き口を下にし
ておく。

3 酒をふり、蓋かラップをして電子レンジで 600W7 分温める。
(取り出す時熱いので注意する)。
4 ポン酢の材料を混ぜ合わせておく。
5 温めた豚肉に 4 をかけて出来上がり。
〜おすすめレシピその2〜
【簡単スイートポテト】

さつまいもはビタミン C・E を含み抗酸化作用が期待できます。食物繊維も豊
富なので、便秘予防にもなります。自分で作ると甘さを調節できるメリットが
あります。満腹感もあるので、ダイエット中のおやつにもピッタリ!小分けに
せず、大きい容器にまとめて入れて作ることによって時間も短縮できます。
さつまいもの甘さを感じられる 1 品になりました!
材料 4 人分
・さつまいも…1 本(230g)
・バター…10g
・牛乳…大さじ 1
・グラニュー糖…大さじ 1
・卵…1 個
作り方
1 さつまいもは皮を剥き、輪切りに切って少ない水で柔らかくなるまで茹で
る。
2 オーブンを 210 度に温めておく。
3 さつまいもが柔らかくなったら牛乳、グラニュー糖、卵、電子レンジで温
めたバターを入れて滑らかになるまで混ぜる。
この時、卵は卵黄と卵白に分けて、焼く前に塗る卵黄を少しだけ残してお
く。
4 オーブン対応の容器に入れて、卵黄を塗り、10 分焼く。
【参考書】
・旬の野菜の栄養事典
以上

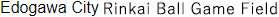
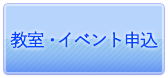
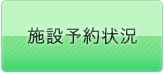

























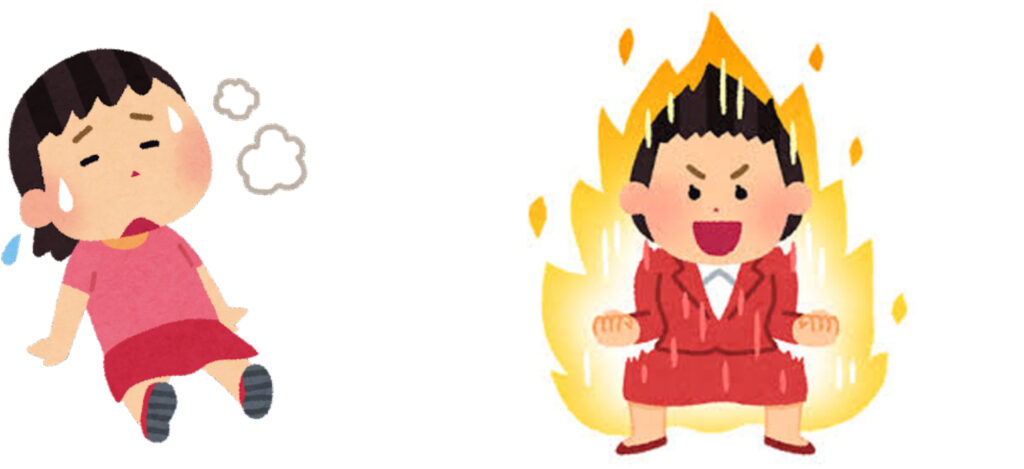


 れんこんは蓮の地下茎を食用とします。粘質物を含み、切ると糸を引くが、酢
れんこんは蓮の地下茎を食用とします。粘質物を含み、切ると糸を引くが、酢




 江戸川区と言えば「小松菜!」は有名ですよね。「サラダ小松菜」という商品
江戸川区と言えば「小松菜!」は有名ですよね。「サラダ小松菜」という商品